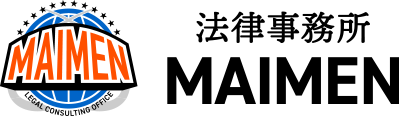労働者側の法律問題
会社に正社員、従業員として勤めているが(あるいは勤める予定だが)、賃金の支払や労働時間等について会社側に問題がある、ある日突然解雇を宣告されたが、日ごろの業務の状況からして解雇には納得できない、というような場合など、労働関係における諸々の問題については以下のような法律的解決が可能です。
(1)内定・試用期間における問題
①内定の取消し
一般に、会社に正式に就職する前に、「内定」というものが出されますが、この「内定」は、法律的には、立派な労働契約です。
ただ、就労開始までに、就労ができなくなった場合(たとえば、留年、病気・けがによる就労不能)に、これを理由に会社側が労働契約を解約できるという条件がついているところに通常の労働契約との差があります。
もっとも、労働契約であることには変わりがないので、内定取消しについては、法律上、解雇する場合に準じた規制がなされることになります。
したがって、会社が内定を取消す(=条件付の労働契約を解約する)場合には、合理的な理由が必要となるため、何らの理由なくあるいは不合理な理由により内定を一方的に取り消された場合には、その行為の適法性を争うことが可能です。
ただし、どのような場合に内定取消が違法になるかは、ケース・バイ・ケースです。
②試用期間後の本採用拒否
大多数の企業においては、正社員の採用について、入社後一定の期間を試用期間あるいは見習いとして、この期間中に正規従業員としての適格性を判断し、本採用をするかどうかを判断するという制度が採られています。
この「試用」も法律上はれっきとした労働契約です。
ただ、適格性について試用期間中に問題が発覚した場合に、会社がそれを理由に労働契約を解約できるというところに通常の労働契約との差があります。
もっとも、やはり労働契約であることには変わりがないので、試用期間後の本採用拒否については、法律上、解雇する場合に準じた規制がなされることになります。
したがって、会社が本採用を取消す(=条件付の労働契約を解約する)場合には、試用制度の趣旨に照らして合理的な理由が必要となるため、何らの理由なくあるいは不合理な理由により本採用を一方的に拒否した場合には、その行為の適法性を争うことが可能です。
ただし、どのような場合に本採用拒否が違法になるかは、ケース・バイ・ケースです。
(2)給与に関する問題
会社に雇われて労働する場合、労働の対価として賃金が支給されます。
この賃金は、毎月一回以上、決まった日に支給されることが法律上要求されています(労働基準法24条2項)。
したがって、毎月1回の給料日が過ぎているのに会社が賃金の支払をしてくれない場合には、その未払賃金について、内容証明郵便等により支払請求をすることが可能です。
書面で請求しても支払われない場合は、訴訟によって支払を強制することが可能です。
この賃金請求権は、2年間で時効によって消滅してしまうので、未払賃金があることが発覚したら、早めに対応するよう注意しましょう。
また、決められた労働時間(たとえば9時~17時)を超えて労働を余儀なくされた場合(いわゆる残業)や休日に出勤をした場合には、法律上、通常の賃金の額に一定の割合を増した額(いわゆる割増賃金)の支払を受けることができます(労働基準法37条)。
このような割増賃金の支払いについては、会社側の法律の不知等により適法な賃金が支払われていないという場合があるので、その場合にも、未払賃料が発生することになります。
適法な割増賃金が支払われているかどうかは、一見して判断することが困難な場合も少なくありません。
(3)労働時間に関する問題
法律上、雇い主である会社は、原則として、労働者を、休憩時間を除いて、1日8時間、1週間に40時間までしか労働させることができないとされています(労働基準法32条1項・2項)。
ただし、例外として、労使間で時間外・休日労働協定が締結されている場合には、その協定で定める範囲において、法定の労働時間を超えて労働させたり、法定の休日に労働させたりすることも可能です。
いわゆる残業は、このような協定の存在が前提となっているものです。
もっとも、時間外労働や休日労働については、割増賃金を支払うことが法律上要求されているので(労働基準法37条)、適法な割増賃金が支払われていない場合には、未払賃金を請求することができます(上記(2)参照)。
また、フレックスタイム制などの変則的な労働形態が採られている場合も、1日8時間、1週間40時間労働の原則の例外となります。
法律に従った労働時間が採用されているか、例外的に法定労働時間を超えて労働をさせている場合に適法な割増賃金が支払われているかどうかは、その判断が困難な場合も少なくありません。
(4)配置変更・転勤等に関する問題
会社においては、必要に応じて従業員の配置変更や転勤命令がなされます。
しかし、雇い主であるからといって、これらの配置変更・転勤命令を無制限に行うことは許されません。
たとえば、会社とある従業員との間で、採用時に職種や勤務地を限定する内容の特約がなされていた場合には、会社は、事実上の必要が生じても、その従業員に対して配置変更や転勤命令をすることはできません。
また、そのような特約がない場合であっても、配置変更・転勤命令が不当な動機・目的をもってなされたものである場合や、配置変更・転勤によりその従業員が被る不利益が著しく大きい場合などには、会社による配置変更・転勤命令は、権利の濫用として違法・無効なものとなります。
配置変更・転勤命令が違法・無効な場合には、従業員はもとの勤務部署・勤務地で働き続けることができます。
また、配置変更・転勤命令を拒んだ従業員を解雇にするという場合もありますが、配置変更・転勤命令が違法・無効であれば、そのような理由によってなされた解雇も違法・無効なものとなります。
どのような場合に、配置変更・転勤命令が違法なものとなるかは、諸々の事情を総合考慮して判断されるものであるため、ケース・バイ・ケースです。
(5)懲戒処分に関する問題
従業員に業務命令違反や職場規律違反・不正行為等があった場合には、その者に対し、懲戒処分(懲戒解雇・諭旨解雇・休職・出勤停止・減給・戒告、訓告、譴責等)がされることがあります。
しかし、従業員の行為に問題があったとしても、懲戒処分が無制限に許されるわけではなく、一定の場合には、懲戒処分が違法・無効なものとなる場合があります。
すなわち、従業員のある行為が就業規則に規定された懲戒処分事由に該当しない行為であるにもかかわらず懲戒処分を行った場合、懲戒処分事由には該当するが、選択された懲戒処分の種類が不当に重いものである場合(たとえば数回の欠勤について、戒告や減給処分ではなく、いきなり懲戒解雇がされた場合)などには、いずれも懲戒処分が違法・無効なものとなります。
どのような場合に懲戒処分が違法・無効となるかの判断は、専門的知識を要することが少なくありません。
(6)解雇に関する問題
従業員の勤務状況等に問題がある場合、あるいは会社の経営状況に照らして人員を削減する必要がある場合、従業員が解雇されることがあります。前者を懲戒解雇、後者を整理解雇と呼びます。
懲戒解雇は、懲戒処分の一種であることから、懲戒解雇に関する法律問題については上記(4)と同様となります。
整理解雇については、過去の裁判例の積み上げにより、現在では、「整理解雇の4要件」というものが確立され、その4要件が充たされていない場合には整理解雇が無効となるとされています。
具体的には、
①会社の経営状況等に照らし整理解雇をする「必要性」があること、
②会社側が解雇を回避する努力をしたこと、
③誰を解雇するかについての選定基準が合理的であること、
④労使間における交渉等、解雇にいたる手続が妥当なものであったこと、
の4つが要件とされています。
これらの要件を充たすか否かは具体的な事情を総合して判断されるので、整理解雇の適法性を一概に判断するのは困難です。
雇い主側の法律問題
上記(労働者側の法律問題)にあるように、労働者側の抱える法律問題にはさまざまな法律問題がありますが、これは裏を返せば、雇い主としての会社が抱える問題でもあります。
会社としては、常に法令の遵守(コンプライアンス)に気を配り、これらの労働問題が生じないように労務管理をすることが望ましいといえます。
労務管理の具体的内容としては、法令に則った就業規則を作成すること(一定の場合には就業規則の作成が要求されない場合があります)、法令に則った労働時間の設定・賃金の支払を行うことが必要でしょう。
また、配置変更・転勤命令等の業務命令を行う場合や、懲戒処分を行う場合に、これらが適法・有効なものといえるかどうかにつき、法的視点からの配慮・検討を行っておく必要があるでしょう。